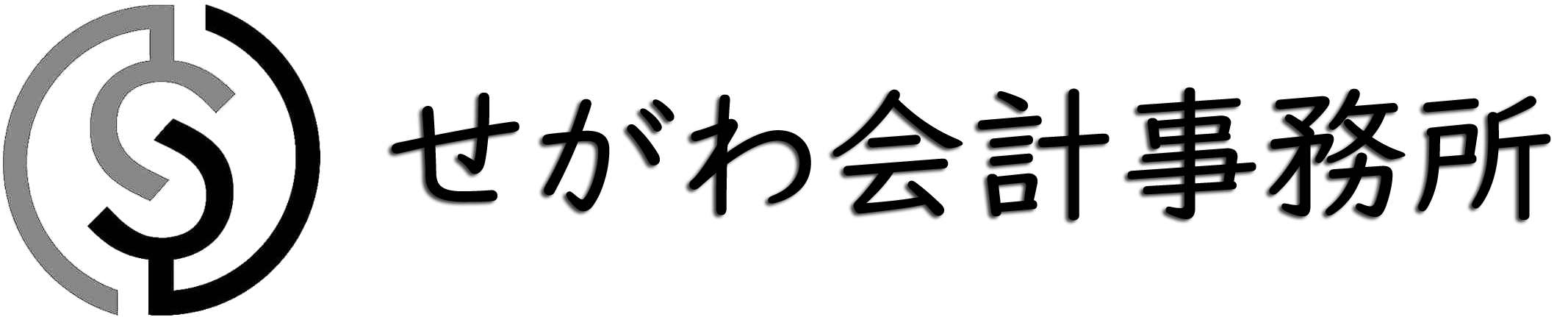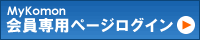SNSを通して皆様のお役に立つ情報の発信もしております。
【税務調査の連絡】その時どうする?税務調査の流れと対応策をやさしく解説!
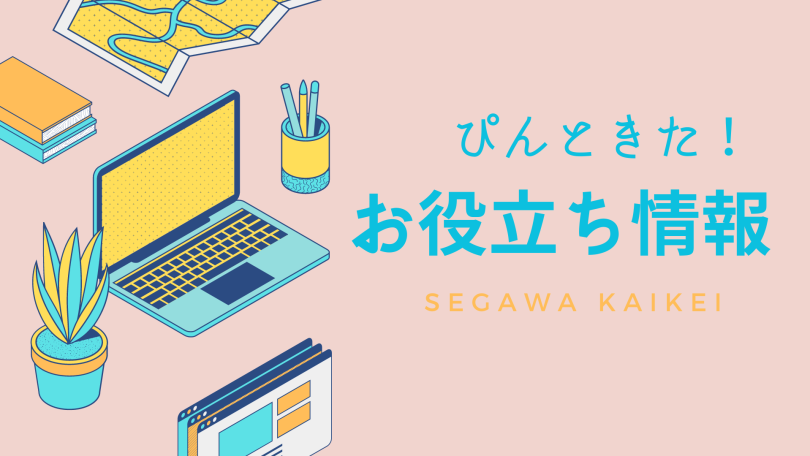

第1章 税務調査の連絡が来た!まず確認したい3つのこと
ある日突然、税務署から「税務調査のご連絡です」と電話が入ると、思わず身構えてしまう方が多いと思います。
ですがご安心ください。
税務調査には明確なルールと段取りがあり、正しい対応をすれば、必要以上に恐れるものではありません。
ここでは、調査の連絡が入ったときにまず確認しておきたい「3つのポイント」を、税理士の視点からわかりやすく解説します。
1-1. 税務署からの連絡は“電話”が基本です
税務調査は、突然訪問されるのではなく、まず税務署からの電話連絡によって調査の意向が伝えられるのが通常の流れです。
この連絡は、納税者本人に直接来ることもありますが、税理士が関与している場合は、税理士に連絡が入るのが一般的です。
電話の内容では、調査の対象となる年度や税目、日程の候補などが伝えられ、税理士がクライアントと相談しながら日程を調整していきます。
税理士が関与している場合は、この時点で慌てる必要はありません。
税理士が窓口となって対応することで、安心して準備を進めることができます。
1-2. 調査内容の通知は、電話での口頭説明が主流です
かつては、税務署から「事前通知書」と呼ばれる書面が届くこともありましたが、現在では、原則として電話での口頭説明による通知が主流となっています。
税務署の職員は、調査の日時・場所・対象税目・対象期間・必要書類などを口頭で説明し、税理士または納税者に確認を取ります(国税通則法第74条の9参照)。
調査の目的や必要な帳簿の範囲について不明点がある場合は、税理士が適切に確認・照会しますので、納税者がすべてを判断する必要はありません。
どこまで準備すればいいか不安な方も、税理士と一緒に進めていくことで、スムーズな対応が可能です。
1-3. 都合が悪い場合は、日程変更もできます
「ちょうど決算対応で多忙」「担当者が不在」「葬儀などの私的事情」など、
調査予定日に都合がつかないこともあるかもしれません。
このような場合には、合理的な理由があれば、調査日程を変更することが可能です(国税通則法第74条の9第2項)。
実際、国税庁のFAQでも「入院・葬儀・業務繁忙期などは配慮される」と記載されています。
税理士が間に入ることで、調査官とのやり取りもスムーズに行えますし、余計な誤解を防ぐことにもつながります。
「変更はできない」と思い込まず、必要があれば遠慮なく相談してみましょう。
第2章 税務調査当日の流れと、知っておきたい対応マナー
税務調査の当日は「どんな人が来るの?」「いきなり質問されるの?」といった不安があると思います。
でも実際には、税務署の職員も冷静で丁寧な対応をする方がほとんどです。
ここでは、調査当日の流れと、納税者が押さえておきたいマナーや心構えをお伝えします。
2-1. 調査官が来たらまず確認すること
調査官が来たら、まず「身分証明書」と「質問検査証」を提示されます。
これは任意調査の基本手続きです。
調査にあたって納税者には協力義務はありますが、これはあくまで任意調査です。
そのため、無理な回答や即答を求められることはありませんし、必要があれば回答を保留することもできます。
冷静に対応することが何より大切です。
この点で、税理士が同席していれば、調査官とのやり取りも安心して行えるでしょう。
2-2. 調査内容は主に4ステップ
税務調査は「何をどう見られるのか」が不明なため、不安を感じる方が多いものです。
ですが実際の調査は、国税庁が公開している手順に基づいて、次の4つのステップで進められます。
一つひとつは冷静に対応すれば問題ない内容ですので、あらかじめ流れを知っておくことで、安心して当日を迎えられます。
調査の冒頭で行われるのが「概況聴取」です。
これは、会社の業種や規模、取引先の特徴、経理の担当体制などを調査官が把握するための聞き取りです。
たとえば「現金商売が多いですか?」「経理は社内で完結していますか?」など、
日常業務に関する質問が中心となります。
この段階で、調査官は調査の重点ポイントや確認事項を絞り込んでいきます。
構えすぎず、ありのままを伝えることが大切です。
続いて行われるのが、申告内容と帳簿との整合性を確認する「帳簿調査」です。
提出済みの申告書をもとに、会計帳簿、総勘定元帳、請求書、領収書、通帳などを照合し、「正しく記帳されているか」「申告漏れがないか」が確認されます。
過去3年分が対象となることが一般的で、調査対象期間に応じた書類を準備しておくことが求められます。
事前に税理士と必要資料を整理しておくことで、調査もスムーズに進みます。
必要に応じて、実際の業務現場を調査官が見に来ることもあります。
これが「現場確認(または現物確認)」です。
たとえば製造業であれば工場や倉庫、小売業であれば店舗の在庫棚など、
帳簿上の数字と実際の在庫数や設備の有無が一致しているかなどがチェックされます。
また、レジの保管状況や在庫の管理体制など、間接的に経理の正確性を確認する場面もあります。
こうした現場調査は「不正を暴く」というよりも、帳簿との整合性を立体的に確認する工程と捉えるとよいでしょう。
調査の最後に、「物件の留め置き」と呼ばれる処理が行われる場合があります。
これは、調査官が帳簿や書類の一部を税務署に持ち帰って精査する手続きです。
勝手に持ち帰られることはなく、必ず「預かり証」が発行されます。
後日返却されますが、調査対象として重要な資料になるため、大切に管理しておきましょう。
心配であれば、税理士が同席して「どの書類をどの目的で預かるのか」をしっかり確認します。
これらの4つのステップは、いずれも「調査官が必要な確認を適正に行うための基本的な流れ」です。
構えすぎず、わからない点があれば税理士にすぐ相談できる体制を整えておくことが、
安心して対応するための第一歩です。
2-3. 調査官とのやり取りは“記録”を意識して
調査中のやり取りは、なるべくメモを取りましょう。
「何を聞かれたのか」「どの書類を見せたか」を記録しておくことで、
調査後に内容を整理しやすくなります。
これは次回の税務調査の参考にもなりますし、納税者の自衛にもつながります。
税理士が立ち会っていれば、記録も整理され、不要な誤解を防ぐための証拠にもなります。
“調査を受ける”という受け身ではなく、“きちんと対応する”という姿勢を大切にしましょう。
第3章 調査後に待っている3つの選択肢と注意点
調査官が帰っても、税務調査は終わりではありません。
調査結果に応じて、修正申告をするか、異議申し立てをするか、対応不要(=是認)なのかが決まります。
ここでは、調査後の選択肢と、それぞれの注意点を丁寧に解説します。
3-1. 調査結果の説明と「修正申告」のすすめ
調査の結果、申告内容に誤りがあると判断された場合は「修正申告をお願いします」と案内されます。
これは罰ではなく、自主的に修正することで加算税などが軽減される制度です(通則法第65条ほか)。
調査官の指摘内容に納得できれば、早めに修正申告をすることでスムーズな解決が期待できます。
税理士と一緒に、内容の妥当性をきちんと確認したうえで対応しましょう。
3-2. 不服があれば“異議申し立て”も可能
調査官の見解に納得できない場合、「更正通知」後に異議を申し立てることができます。
具体的には「再調査の請求」や「国税不服審判所への審査請求」といった正式な手続きがあります(通則法第75条ほか)。
ただし、これらは期限が決まっており、主張の裏付けも必要になります。
また国税不服審判所では納税者側の敗訴判決が多いため、慎重な判断がもとめられます。
3-3. 調査後こそ“経理改善”のチャンス
税務調査は、経理の問題点を“見える化”する絶好のチャンスです。
申告漏れや記帳ミスの傾向が明らかになったら、それを放置するのではなく、改善に活かすことが何より大切です。
顧問税理士といえども、100%クライアントの隅から隅まで理解・管理ができているわけではないのが本音です。
調査後の振り返りとあわせて「今後のリスクを減らす体制づくり」をブラッシュアップしていくと良いでしょう。
“調査をきっかけに、経理が強くなる”という考え方で、前向きに進んでいきましょう。
🔚 まとめ|税務調査は“乗り越えるもの”ではなく“備えるもの”です
税務調査は、どんなに誠実に経営していても訪れる可能性があります。
けれど、それは「あなたが疑われている」というわけではありません。
正しい知識と専門家のサポートがあれば、税務調査は落ち着いて対応できるものです。
むしろ、調査は会社の経理や体制を見直す貴重な機会です。
未だ税理士がおらず、税務調査のことで不安を感じたときはどうか一人で悩まずに、
お近くの税理士に相談してください。
せがわ会計事務所は、千葉県成田市で主に会社設立・法人運営に特化している税理士事務所です。
経験豊富な税理士がパートナーとしてクライアント様をサポートさせていただきますので、
税務や経営に関するお悩みは、お気軽に当事務所までお問い合わせください♪
 SEGAWA
SEGAWA税務調査は、まず現場(通常であれば2日間、ある程度の規模になりますと3日~1週間ほど)から始まり、その後1か月程度をかけて担当官と税理士とで主に電話等で調査の結果(落としどころ)を詰めます。
事業者様は、この現場にお付き合いいただきます。
税務調査=嫌だ!ではなく、税務調査=無料のコンサルと前向き(?)に捉えていただくと良いかもですね(笑)。