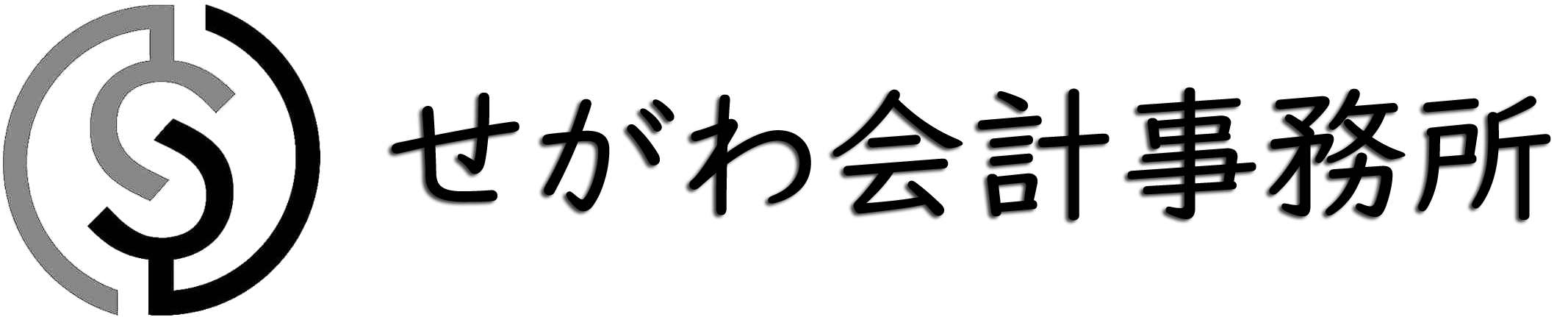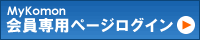SNSを通して皆様のお役に立つ情報の発信もしております。
【2026年施行】退職金控除が変わる!10年ルールで損しないための注意点

第1章 「え?退職金控除って変わるの?」
〜改正の背景と概要をやさしく解説〜
退職金といえば、「長年がんばったご褒美」として非課税や優遇税制があることで知られていますよね。
でも実は2026年から、その“優遇のルール”がちょっと変わるんです。
「なんで今さら?」「私にも関係あるの?」と思われた方、ご安心ください。
ここでは、今回の見直しがなぜ行われるのか、どんな背景があるのかを、税理士の目線からやさしく解説していきます。
1-1. どうして変わるの?控除見直しの背景にある“公平性”の問題
退職所得控除の見直しが行われた最大の理由は、「課税の公平性」を保つためです。
たとえば、退職前に「DC一時金(確定拠出年金の老齢給付金)」を受け取り、5年経過後にお勤め先やご自身で経営されている会社から退職金を受け取ると、両方に退職所得控除がフルに使えてしまうケースがありました。
これだと、勤続年数がかぶっていても二重で控除を受けることになり、不公平になってしまいます。
国税庁としても、「本来一人分の働きに対する控除が二重になっているのはおかしいよね」という判断に至ったわけです。
今後は、よりフェアに退職金の税制を運用していくための調整が行われます。
1-2. これまでの「5年ルール」とは何だったのか?
これまでの制度では、DC一時金を受け取ってから退職金を受け取った年の“前年以前4年以内(5年)”に該当する場合、勤続年数の重複を排除して退職所得控除を調整するルールがありました。
つまり、近い時期に複数の退職所得を受け取ると、同じ勤続年数に対しては控除が一度しか使えない、という考えです。
しかし、5年以上空いていれば調整の対象外となり、両方の退職金に満額の控除が使えてしまう、いわば“グレーゾーン”が存在していました。
同族企業の役員や、高齢者雇用の延長などでこの抜け道を利用しやすくなってきた背景から、見直しが必要とされたのです。
1-3. 2026年からの「10年ルール」は何がどう変わる?
2026年からは、このルールが**「前年以前9年以内(10年)」に延長されます。つまり、退職一時金を受け取った年の“前年以前9年以内”に他から退職金を受け取ると、控除の調整対象となる**のです。
たとえば、60歳でDC一時金を受け取り、70歳で退職一時金を受け取った場合、これまでは「5年以上空いてるからOK」とされたケースでも、新ルールでは“前年以前9年以内”に該当するため、勤続年数の重複排除が適用され、控除は一部しか使えません。
これは控除の二重取りを防ぐための重要な変更です。
退職金の受け取り時期に応じて税額が大きく変わる可能性があるため、あらかじめ知っておくことがとても大切です。
第2章:「知らないと損するかも!」〜実際にどんな影響があるの?〜
制度の改正って、「なんだか難しそう」で済ませてしまいがちですよね。
でも、退職金に関しては“知らなかった”ではすまされない可能性もあります。
特に、確定拠出年金(DC)と退職手当を別の時期に受け取る予定の方は要注意です。
ここでは、「どんな人が影響を受けるのか?」を中心に、具体的な状況を想定しながらお話ししていきます。将来の“手取り”が変わってしまうかもしれない大事なポイント、いっしょに確認していきましょう。
2-1. 退職金とDC一時金、両方もらう人は要注意!
今や多くの方が企業型・個人型DC(確定拠出年金)に加入しており、定年時に「DC一時金」と「退職手当」をそれぞれ受け取るケースが珍しくありません。
でもこの受け取り方、タイミングによっては退職所得控除が満額使えなくなるリスクがあるのです。
2026年以降は、「退職手当を受け取った年の前年以前9年以内」にDC一時金を受給していると、勤続年数が重なった分だけ控除が減らされる仕組みになります。
つまり、両方の退職金を何も考えずに受け取ると、「あれ、思ってたより税金高い…」ということも。
今後は“順番”や“間隔”を意識して計画的に受け取ることが大切です。
2-2. 勤続年数の“重複排除”ってどういうこと?
少し難しそうに聞こえる「勤続年数の重複排除」とは、ざっくり言えば「同じ働いた期間に対しては、退職所得控除を2回使えませんよ」ということです。
たとえば、60歳でDC一時金、65歳で退職手当を受け取ったとしましょう。
実際にはどちらも“同じ会社での勤続年数”が関係していることが多く、これを2回分としてカウントしてしまうと不公平になってしまうんですね。
2026年からは、この“重複排除”の対象期間が10年に延びるため、より多くの人が控除制限を受ける可能性が出てきます。
働いた年数は1回分しか評価されない、という前提を持っておくと安心です。
2-3. 65歳以降の退職に影響大?ケース別シミュレーション
では実際に、いつ退職金を受け取ると損しやすいのでしょうか?
たとえば、60歳でDC一時金をもらい、その後65歳・70歳・71歳で会社などから退職金を受け取った場合を考えてみます。
2026年からのルールでは、65歳・70歳のケースは“前年以前9年以内”に該当するため、退職所得控除が一部制限されます。
しかし71歳なら、DCとの間隔が前年以前9年以上になるため控除の満額適用が可能です。
とはいえ、現実的に71歳まで働くのはハードルが高いですよね。
だからこそ、「退職金はいつ、どう受け取るか?」という設計を早めに考えることが、将来の手取りを守るカギになるのです。
| 年齢 | 受取内容 | 控除の扱い | 結果 |
| 60歳 | DC一時金を受け取る | ー | ー |
| 65歳 | 会社から退職金を受け取る | ❌ 制限あり | 手取 |
| 70歳 | 会社から退職金を受け取る | ❌ 制限あり | 手取 |
| 71歳 | 会社から退職金を受け取る | ✅ 満額適用 | 手取◎ |
第3章:「税理士が教える」〜今からできる3つの備え〜
ここまで読んで、「なんだかちょっと不安になってきた…」という方、ご安心ください。
実は今のうちからできる対策、ちゃんとあるんです。
ポイントは「受け取るタイミング」「書類の扱い」「会社の体制づくり」の3つ。
少し先のことに見えて、退職時の税金対策は“今から準備”が大事です。
税理士の立場から、堅すぎず、でもしっかり役立つアドバイスをお届けします!
3-1. 退職金をもらう“時期”を意識しておこう
退職金って、ただ「定年になったからもらう」だけじゃダメなんです。
特にDC一時金と合わせて受け取る予定がある場合は、“いつ受け取るか”が手取り額に直結します。
2026年からは、「退職手当を受け取る年の前年以前9年以内」にDCを受け取っていると、控除が制限される可能性があります。
この“9年の壁”を意識して、退職時期やDCの受け取りタイミングをしっかり計画しましょう。
退職金は人生最後の大きなお金。だからこそ、ちょっと先のことを読む力が大事です。
3-2. 必要書類の保存期間にも変更あり!10年ルールとは?
今回の改正で地味に大きなポイントがもうひとつ。
それは、「退職所得の受給に関する申告書」の保存期間が7年→10年に延長されたことです。
この申告書は、DC一時金を退職所得として扱う際に必要なもので、税金の計算に大きく関わります。
「そんな昔の書類、もうないよ…。」となってしまうと、思わぬ課税リスクに。
これから受け取る方も、すでに受け取った方も、10年は大切に保管しておきましょう。
「紙1枚で数十万円の差」が出ることもありますよ!
3-3. 税務署への提出義務の拡大、会社側の対応はどうする?
これまで、退職所得に関する源泉徴収票の提出義務は“役員”に限られていましたが、2026年からはすべての居住者に対して提出が義務化されます。
つまり、今後は社員や契約社員の退職金に関しても、企業は源泉徴収票を必ず税務署に提出しなければなりません。
中小企業では「そこまでやってなかった…」という声もあるかもしれませんが、税務調査でもチェックされるポイントになります。
会計事務所と連携して、退職金支給時の業務フローを今のうちに見直しておくと安心です。
「うちの会社は大丈夫?」と思った方、まずは顧問税理士に相談してみてくださいね。
最後に
退職金って、人生のごほうびみたいなもの。
だからこそ、「知らなかった…」で損をしないように、今から備えておくことが大切です。
制度は少しずつ変わっていきますが、しっかり理解すればこわくありません。
「自分の場合はどうなるんだろう?」「今からでも将来設計をしたい!」と思った方は、ぜひ一度、税理士などの専門家に相談してみてくださいね。
将来の手取りを守るのは、今のあなたの一歩です。あなたの安心退職ライフを、応援しています!
せがわ会計事務所は、千葉県成田市で主に会社設立・法人運営に特化している税理士事務所です。
経験豊富な税理士がパートナーとしてクライアント様をサポートさせていただきますので、
税務や経営に関するお悩みは、お気軽に当事務所までお問い合わせください♪
 SEGAWA
SEGAWAこれまでの退職金受取は、先にDCを受け取り5年経過後に会社から退職金を受け取るのが節税のセオリーでした。
これが10年となると、、、なかなか厳しい策ですね💦。
DCの退職金を10年間NISAなどで非課税運用させる、、、といった対策が必要となりますので、今後ますます投資リテラシーを上げていく必要がると思います。