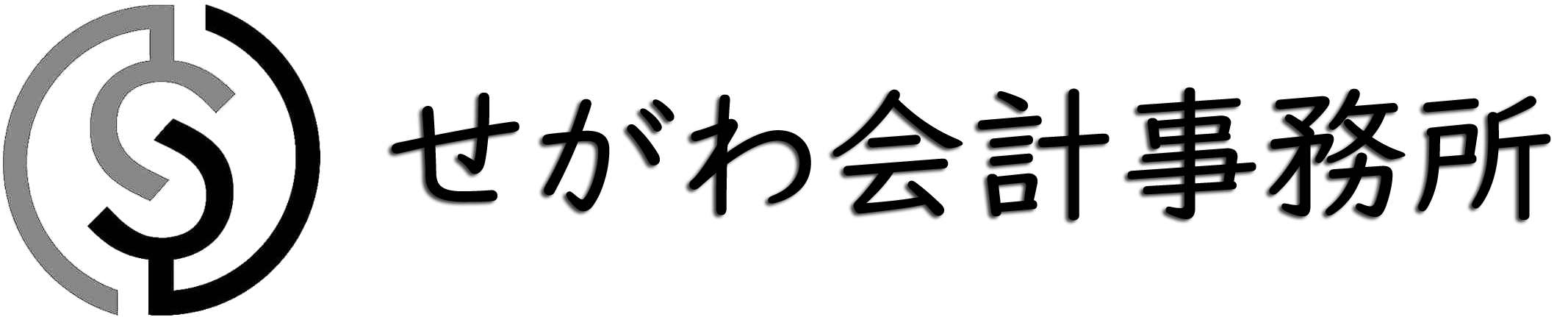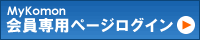SNSを通して皆様のお役に立つ情報の発信もしております。
【要注意】インボイス登録を取り消すには? 取消手続きと2年・3年縛りの落とし穴

第1章 インボイス登録をやめたいと思ったら知っておきたい基礎知識
インボイス制度が始まってから、「登録したものの思った以上に負担が大きい」と悩む方は少なくありません。特に小規模事業者では、売上が基準期間で1,000万円以下になっても、一度インボイス発行事業者として登録すると、その効力が続く限り消費税の申告・納付義務はなくならない点が大きな落とし穴です。
つまり、売上規模が小さくても課税事業者として扱われ続けるため、登録を取り消すかどうかの判断は非常に重要です。
この記事では、登録取り消しのルールや「2年縛り・3年縛り」といった制度の制限、免税事業者に戻るための実務ポイントを、税理士の視点からわかりやすく解説します。
インボイス登録は「すぐ取り消せるだろう」と軽く考えると、後で大きな負担を背負う可能性があります。まずは基本的な違いや手続き、よくある誤解を整理しておきましょう。
1-1. インボイス発行事業者と免税事業者の違いをやさしく解説
インボイス発行事業者は「適格請求書」を発行でき、取引先に仕入税額控除のメリットを提供できます。
ただし、登録の効力が続く限り、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になっても消費税の申告・納付が必要になります。
一方、免税事業者は売上が一定以下であれば消費税の納付が免除されますが、インボイスを発行できないため、取引先から不利に扱われることもあります。
1-2. 「登録取消届出書」と提出期限15日前ルール
登録を取り消すには「登録取消届出書」の提出が不可欠です。
取り消したい日の属する課税期間開始日の15日前までに提出しなければならず、1日でも遅れると翌々課税期間からの効力になります。
結果として、課税事業者としての期間が1年延びてしまうリスクがあるため、期限管理は非常に重要です。
1-3. 税理士が見てきた“よくある後悔”と誤解
「売上が減ったから翌年は免税に戻れるだろう」と誤解して登録した結果、2年縛りや3年縛りに縛られて後悔する方は少なくありません。
また「免税事業者でもインボイスを発行できる」と思い込んでいる方もいます。
こうした後悔を防ぐには、制度の仕組みを正しく理解し、事前に専門家へ相談することが何より大切です。
第2章 取り消しのルールと「2年・3年縛り」の正体
インボイス登録の取り消しには、制度上のルールが存在します。
特に「2年縛り」と「3年縛り」は、免税に戻る際の大きな障害です。
2-1. 経過措置を利用した登録に潜む「2年間は戻れない」縛り
免税事業者が経過措置を利用してインボイス登録をした場合(課税事業者選択届出書を提出せずに、適格請求書発行事業者の登録申請書のみの提出して課税事業者となる場合)、少なくとも2年間は課税事業者を続けなければなりません。
例えば令和6年に登録した場合、令和8年末までは納税義務が継続します。
「思ったより負担が大きいから翌年は免税に戻したい」と考えても、制度上は不可能です。
さらに、登録をやめるには「登録取消届出書」を期日までに提出する必要があり、遅れると効力は翌々課税期間からとなり、課税事業者の期間がさらに延びてしまいます。
2-2. 固定資産取得で発生する「3年縛り」と実務上の落とし穴
事業者免税点制度および簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に、高額特定資産を購入して消費税の申告を受けた場合には、3年間は免税に戻れない制限があります。
節税のための設備投資が、結果として「3年間の課税事業者縛り」につながることもあるのです。
実務では、設備投資後に「やはり免税に戻りたい」と希望されても戻れないケースがよくあります。
投資判断の前にインボイス登録との関係を確認しておくことが大切です。
2-3. 課税事業者がインボイス登録した場合は縛りがないケース
もともと課税事業者がインボイス登録した場合には、経過措置による2年縛りは適用されません。
これは、そもそもこのケースでは経過措置の適用(免税事業者がインボイス登録により課税事業者になる措置)の対象ではないからです。
登録をやめたい場合は、課税期間開始の15日前までに届出をすれば、翌課税期間から免税に戻ることができます。ただし、提出が遅れると翌々課税期間からしか効力が発生しません。
「課税事業者ならすぐ戻れる」と思い込まず、期限をしっかり意識して行動する必要があります。
第3章 免税事業者に戻るための実務ポイントと判断基準
免税事業者に戻るには「届出を出すだけ」と考えがちですが、実際にはタイミングや他制度との関係も踏まえて判断する必要があります。
3-1. 取消届を出してもすぐ戻れない?タイミングの見極め方
取消届を提出しても、免税に戻れるのは翌課税期間からです。
さらに届出が遅れると翌々課税期間からしか効力が及ばないため、課税事業者としての期間が1年以上延びてしまうリスクもあります。
戻るタイミングを見極め、逆算してスケジュールを立てることが欠かせません。
3-2. 2割特例・簡易課税制度との関係と有利不利の判断
免税に戻る前に「2割特例」や「簡易課税制度」の活用を検討することで、課税事業者を続けながら負担を軽減できる場合があります。2割特例は小規模事業者の税負担を抑える制度であり、簡易課税制度も業種によっては有利になる可能性があります。
免税に戻るのか、制度を活用しながら課税事業者を続けるのか、比較検討が重要です。
3-3. 税理士がアドバイスする「取り消しを検討すべきタイミング」
基準期間の売上が1,000万円以下に落ち着いたBtoC業者や、主要な取引先からインボイスを求められなくなった事業者は、取り消しを検討すべき好機です。
さらに、設備投資の予定や資金繰りの状況によっても判断は変わります。焦らず事業全体を見渡し、専門家に相談して最適なタイミングを選ぶことが、無駄な負担を避ける近道です。
🔚 まとめ|
インボイスの登録制度には「2年縛り」「3年縛り」といったルールがあり、売上が1,000万円以下になっても登録の効力が続く限り消費税の申告・納付が必要です。
さらに、取消届を提出するタイミングを逃すと免税に戻れる時期が1年延びることもあります。
だからこそ、制度の仕組みを正しく理解し、慎重に判断することが欠かせません。
私たち税理士は国税庁の最新情報をもとに、事業の実態に即した最適なアドバイスを提供いたします。
成田市や近隣地域(富里市・佐倉市・八街市・印西市・香取市・多古町・芝山町など)でインボイスや消費税にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
 SEGAWA
SEGAWAインボイス制度が導入して数年たちまして、そろそろ取消を検討される方もいらっしゃるのではないでしょうか?
とくに理美容業など個人客を相手にする事業者様は、該当してくると思います。
登録取消については、まず自社がどのタイミングで登録したかによって2年縛りの有無を判定しますので、ギリギリになってから行動するのではなく、税理士と相談のうえ余裕をもって判断・届出を行うことが大事です。