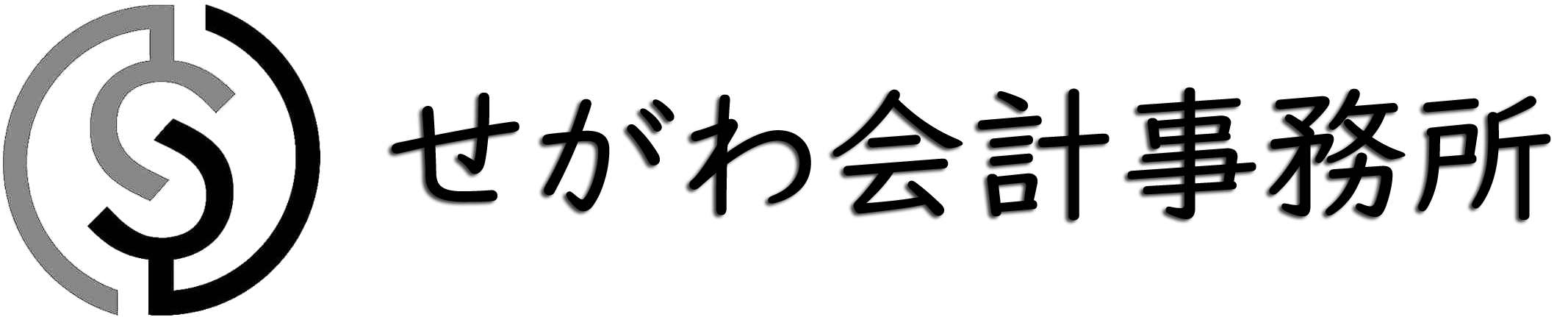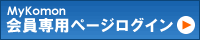SNSを通して皆様のお役に立つ情報の発信もしております。
【要確認】福利厚生費でよくあるNG例と、税務調査で否認されないための対策

第1章 「福利厚生費」のつもりが落とし穴?よくある誤解と見落とし
福利厚生費は、社員満足と節税の両立ができる「企業にとってありがたい費用」ですが、税務上はとてもシビアに見られます。
「社員のために使ったからOK」ではなく、“税務署が納得する形”であることが重要です。
まずは、意外と見落とされがちな“福利厚生費の3つの基本原則”と、その誤解されやすいポイントを整理しましょう。
1-1.「一部の社員対象」はNG!“全従業員対象”の原則を忘れずに
福利厚生費は、「全社員に公平に提供されていること」が大前提。
たとえば、役員や役員親族・特定の部署だけを対象にした飲食代や贈答品は、たとえ名目が“社内レクリエーション”であってもアウトです。
国税庁も「全従業員を対象としていない場合は福利厚生費に該当しない」と明記しています。
社員全員が自由に参加・利用できる制度であることが、否認リスクを避けるポイントです。
1-2. 商品券や現金支給はNG!換金性の高い支給は給与扱いに
「感謝の気持ちで商品券を渡した」――
その気持ちは素晴らしいのですが、税務上では“現金に近いもの”=給与課税の対象です。
商品券・プリペイドカード・ギフト券などの支給は、
現金で給与を支給した場合と実質的には同じことになります。
そのため、これらを役員・従業員等へ手渡しした場合には、原則として
給与課税&源泉徴収の対象となります。
これを福利厚生費で処理すると、税務調査で否認→追徴のリスクが発生します。
「物」ではなく「金銭や金券類」は、原則給与扱いと覚えておきましょう。
1-3. 「福利厚生費」として処理しても、実態が伴わなければ否認される
帳簿に「福利厚生費」と書いてあっても、それだけで安心はできません。
国税庁は、費目ではなく「実態」で判断します。
たとえば、実際には役員の私的会食を「社員慰労会」として処理していたり、家族旅行を「社員旅行」として計上していた場合、調査で否認されるのは当然です。
その場合には、役員給与損金不算入による法人税、所得税、延滞税のトリプルパンチ課税が待ってます…。
支出の名目と中身が一致しているか――日ごろからの確認が、最大のリスク対策です。
第2章 税務調査で狙われやすい!否認されやすい福利厚生費のNG実例
社員旅行は、福利厚生費として認められやすい一方、国税庁が明確な判断基準を示しています。
具体的には、①旅行日数、②対象範囲、③参加割合であること。
これらを満たさないと、給与扱いや交際費扱いになる可能性が出てきます。
「うちは毎年恒例だから大丈夫」と思わず、内容と運用を一度確認しておきましょう。
2-1. 社員旅行はOK?アウト?判断基準は「4泊5日」「全員対象」「参加割合」
社員旅行や慰安会は、福利厚生費として認められやすい一方、国税庁が明確な判断基準を示しています。
これらを満たさないと、給与扱いや交際費扱いになる可能性が出てきます。
「うちは毎年恒例だから大丈夫」と思わず、内容と運用を一度確認しておきましょう。
2-2. 社員食堂・昼食補助が給与とされる境界線とは?
社員食堂や昼食補助制度も、金額や負担割合によっては給与課税の対象になります。
国税庁は、会社の補助額が月3,500円以下であること、かつ従業員がその半額以上を自己負担していることを条件としています。
会社が全額負担したり、補助が過剰になると給与扱いになる可能性があります。
「感謝のつもりが課税対象に」――そんな事態を防ぐためにも、制度設計に注意が必要です。
2-3. 慶弔金・見舞金・福利施設…“厚意”が“課税対象”に変わる瞬間
出産祝いや弔慰金、人間ドックの費用補助などは、福利厚生の一環として一般的ですが、対象者が限られていたり、社会通念上と照らして金額が過大だと、否認される可能性があります。
また、社内・社外施設(ジム・ラウンジ・会員制バー・ゴルフ会員権など)も、
特定の社員しか使えない設計になっていると“福利厚生”とは認められません。
あくまで「誰でも使える」「過度でない」ことが判断のカギ。
制度の設計は、社内の公平性と税務上の視点を両立することが求められます。
第3章 税務署にも社員にも認められる!福利厚生費の運用チェックリスト
「否認されない福利厚生費」にするには、制度そのものの見直しと証拠書類の整備が不可欠です。
ここでは、企業がすぐに確認・実践できる運用ポイントを3つご紹介します。
社員にも税務署にも信頼される福利厚生制度は、会社の“見えない資産”でもあります。
3-1. 判断基準は「全社員に共通」「社会通念上の金額」「換金性なし」
この3つが、福利厚生費の根本的な判断軸です。
特定の社員だけが対象になっていたり、金額が過大だったり、金券類で支給されたりすると、
否認リスクが高まります。
「うちはどうだろう?」と思ったら、まずはこの3項目をチェックしましょう。
制度設計の基本を押さえることで、リスクは確実に減らせます。
3-2. 交際費?給与?福利厚生費?グレーな経費の“線引き”ルール
たとえば「取引先の親族に不幸があり、香典として現金を支給した」――
この場合、交際費として処理すべきです。
名目ではなく、“誰のための支出か”で判断されるのが税務の特徴。
給与・交際費・福利厚生費の違いがわかるだけで、税務のトラブルを大きく減らせます。
処理が曖昧になっている経費は、税理士に相談しながら線引きを明確にしましょう。
3-3. 税理士と一緒に「社内ルール」と「証拠書類」を整えておこう
制度があっても、それを説明できる記録や書類がなければ、税務署には通じません。
支給基準、対象範囲、社内通知、出席者名簿、写真や議事録など――すべてが“証拠”になります。
「整えるのが大変…」と感じたら、税理士と一緒にチェックリスト形式で整備するのもおすすめです。
準備こそが、最大の防衛策です。
🔚 まとめ|“社員想い”の制度を“税務署想い”にも整えておこう
福利厚生費は、会社の思いやりが形になる大切な費用。
でも、その善意が「税務署に通用するか」は別問題です。
だからこそ、制度の対象・金額・証拠の整備――この3点を押さえて、社員にも税務署にも“正しく伝わる福利厚生”を目指しましょう。
もし少しでも不安な点があるなら、税理士と一緒に制度を見直すことをおすすめします。
せがわ会計事務所は、千葉県成田市で主に会社設立・法人運営に特化している税理士事務所です。
経験豊富な税理士がパートナーとしてクライアント様をサポートさせていただきますので、
税務や経営に関するお悩みは、お気軽に当事務所までお問い合わせください♪
 SEGAWA
SEGAWA中小企業の皆様は給与を上げたいと思っても、
上げた給与は下げられない..というジレンマを抱えてますよね。
その場合は、まずは給与課税されないような
【福利厚生制度の導入】を積極的に検討されてみては
いかがでしょうか?
ちなみに社長・親族だけのプライベートカンパニーで、福利厚生制度を導入しても、基本的にはNGです。
実務でもトラブルになりますので、注意してくださいね。